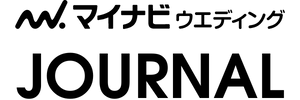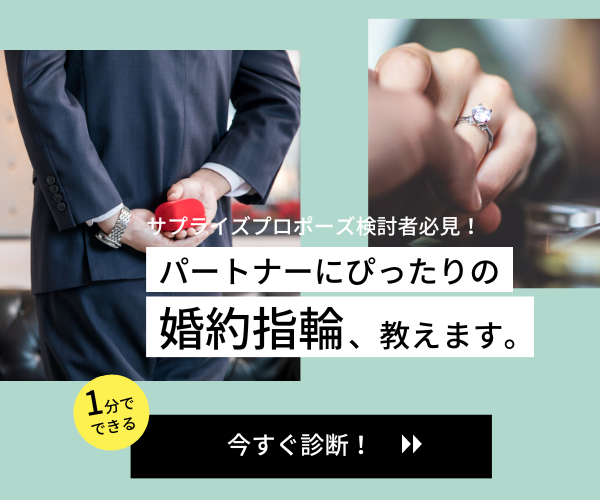「縄文人は結婚していたのか?」縄文時代を愛する男がたどる「1万年の足跡」
2025/06/18 更新
※この記事は2016年にKekoon powered by マイナビウエディング にて配信されたものです
縄文時代。
それは、日本人のルーツとされる人々が獲物を追って移動を繰り返す遊動生活から、竪穴式住居を拠点とする定住生活に移行した時代。
紀元前の昔に約1万年間続いたとされるこの時代に、もし「結婚」という概念があったとするなら、どのようなものだったとみなさんは考えますか?
申し遅れました、ライターの根岸達朗です。
本日は我々の偉大な祖先が歩んできた道から、原始的な結婚の形を考えます。話を聞いたのは、都会の縄文人のためのフリーマガジン「縄文ZINE」の編集長・望月昭秀さん。今日はよろしくお願いします。
根岸「単刀直入に聞きます。縄文人は結婚していたんですか?」
望月さん「その時代に生きたことがないので分かりません」
全人類が未確認。
それが、縄文人の結婚。
【話を聞いた人】

望月昭秀(もちづき・あきひで)/「縄文ZINE」編集長。縄文時代好きが高じて、2015年に同誌を創刊。株式会社ニルソンデザイン事務所代表
縄文ZINE
http://jomonzine.com/
それは、日本人のルーツとされる人々が獲物を追って移動を繰り返す遊動生活から、竪穴式住居を拠点とする定住生活に移行した時代。
紀元前の昔に約1万年間続いたとされるこの時代に、もし「結婚」という概念があったとするなら、どのようなものだったとみなさんは考えますか?
申し遅れました、ライターの根岸達朗です。
本日は我々の偉大な祖先が歩んできた道から、原始的な結婚の形を考えます。話を聞いたのは、都会の縄文人のためのフリーマガジン「縄文ZINE」の編集長・望月昭秀さん。今日はよろしくお願いします。
根岸「単刀直入に聞きます。縄文人は結婚していたんですか?」
望月さん「その時代に生きたことがないので分かりません」
全人類が未確認。
それが、縄文人の結婚。
【話を聞いた人】

望月昭秀(もちづき・あきひで)/「縄文ZINE」編集長。縄文時代好きが高じて、2015年に同誌を創刊。株式会社ニルソンデザイン事務所代表
縄文ZINE
http://jomonzine.com/
目次
目次を開く
縄文時代の「モテ」を考える

望月さん「研究されている方々はいますけど、その方々も実際に見たわけではないですからね。だからあくまでもこうだったんじゃないかって話になる。基本的にヒントしかないんですよ、縄文時代って」
根岸「では、今日はそれを踏まえて想像を膨らませてみたいです。さっそくですが、結婚にもつながる『モテ』から考えたいなと。縄文時代ではどんなヤツがモテたと思いますか?」
望月さん「男はやっぱり狩猟がうまいヤツじゃないですか」
根岸「狩猟ですか。でも狩猟とはいっても、マンモスにみんなで石投げて倒すとかそういう原始的な方法だったんじゃないんですか?」

望月さん「日本の縄文時代にマンモスいませんよ。いたのは氷河期と言われる時代。氷河期は、縄文時代の前にあたる旧石器時代に重なっています」
※紀元前~紀元後初期の時代区分(諸説あり)
旧石器時代(一部氷河期)・・・紀元前14000年頃
縄文時代・・・紀元前14000年頃 - 紀元前400~300年頃
弥生時代・・・紀元前400~300年頃 - 200~300年頃
古墳時代・・・200~300年頃 - 700年頃
旧石器時代(一部氷河期)・・・紀元前14000年頃
縄文時代・・・紀元前14000年頃 - 紀元前400~300年頃
弥生時代・・・紀元前400~300年頃 - 200~300年頃
古墳時代・・・200~300年頃 - 700年頃
「昔学校でそんなようなことを習った気もするのですが、完全に忘れました。じゃあ、その時代に狩っていたものというと?」
望月さん「イノシシでしょう。すばしっこいのもいたでしょうから、弓矢に毒塗ったりしてそれなりのテクニックで倒してたと思いますよ。あとこの時代は旧石器時代に比べて植生が豊かになっていて、どんぐりや栗がたくさん採れたんです。青森の三内丸山遺跡では、みんなめちゃくちゃどんぐり食べてたことがわかってますね」

「じゃあイノシシを狩るのがうまいとか、木の実を集めてくるのがうまいとか、そのあたりの総合ポイントでモテたと考えていい?」
望月さん「そうですね。でも、単純に運動神経がいいとか、体力があるとかだけではなかったと私は思っています。アイヌってご存知ですか?」
根岸「あ、北海道の先住民族ですよね。縄文人とどんな関係が?」
望月さん「実はアイヌって、今の日本で縄文の遺伝子が一番濃いんです。生業も縄文人と同じ狩猟採集ですし、彼らの文化を紐解くと、一緒じゃないにせよ多少は縄文のことが見えてくるんじゃないかと」
根岸「おお、なるほど。たとえばどんな文化があるんですか?」
望月さん「彼らは言葉の民と言われていて、言葉でいろんなことを表現しています。そのなかに『チャランケ』という揉め事の解決法がある。集落の大事なことや問題はそれで決めるんですけど、一人が主張しているときに、相手は決してそれに口を挟まないんですね。とにかく聞く」
根岸「コミュニケーションの基本ができてますね」
望月さん「ただ、そのやり方がけっこうすごいらしいんです。それぞれ、故事来歴や、ことわざや、歌や韻文で主張していたらしいんです」
根岸「へえ、そういうパフォーマンスみたいな。それが繰り返されるわけですか?」
望月さん「はい。一人の主張が終わったら、ほかの人という感じで。なんかラップのフリースタイルみたいじゃないですか。このことから思うに、僕は縄文人も知識や、言葉の使い方や頭の回転が早いとか、その種の文化的な要素でモテた可能性もあるんじゃないかと。縄文人に文字はありませんでしたが、言葉はあったはずなので」
根岸「なるほどー。となると、文武両道だったらめちゃくちゃモテたかもしれないですね」
望月さん「狩りだって、大きな獲物にはチーム戦で挑まなければならない時があっただろうし、頭の良さってけっこう重要なんだと思います。なおかつ手先が器用で道具を作るのがうまくて、力があって、狩猟がうまくて『生きる力』があったらそれは最強でしょうね。どちらかに特化していることでの『モテ』もあったかもしれませんし」

「これはあくまでも狩りに出るのが男性とした場合の男性目線の『モテ』だと思うんですが、女性の場合はどうだったんでしょう?」
望月さん「男女の役割で考えると、縄文土器は女性がつくっていたとされているんですよ。『モテ』という観点ではわからないのですが、生活の道具である土器をつくって、子どもを産み、集落の文化を育んできたという意味では、村のアイデンティティを司っていたのは女性だったのではないかと」
根岸「芸術家の岡本太郎先生を唸らせたような土器の凄まじい文様も、女性がつくっていた可能性があるわけですよね」


望月さん「実際、出土された土器の分布傾向から見て、かっこいい土器の文様が広まりやすかったというのはあります。トレンドがあるんですよ。ということは、その中心になるような村もあったはずで、あの村の土器がイケてるからあそこの異性と知り合いになりたい、あわよくばくっつきたいとかもあったんじゃないかと」
根岸「都会に憧れて上京した青年が、中目黒とか代官山あたりに住んでアーバンライフを謳歌している女性に惹かれるとかそういう感じですかね」
望月さん「現代の尺度では捉えらないですが、それに近い感覚もあったかもしれません。もちろん土器をつくるのがうまい男性もいたでしょうし、男性以上に狩りのうまい女性もいたと思います。同性愛の人もいたかもしれない。なにせ縄文時代は1万年もあった。その間にはいろんな出会いの形があったのではないかと」
結婚は「旅立ち」だったのか

望月さん「答えはでないかもしれないけど、まあ考えてみましょう」
根岸「現代には一夫多妻という形もあるわけですが、縄文時代ってそのへんはどうだったと思いますか? 何人と子を残しても、本能的、動物的に言えば正しいともいえるわけで、婚姻という『形』がなかったとしても自然な気もしました。毎日ハプニングバーみたいだったらどうします?」
望月さん「すごいなあと思うだけで、まあ、どうもしないです。ただ、狩猟採集のほかの民族を見るに、縄文人にもある程度の婚姻関係はあったんじゃないかと」
根岸「まあ、確かにその方が社会の秩序は守られそうな気はしますね。ハプニングバーは平和を乱しそうですから」
望月さん「そうですね。でも、結婚はあったと言っても、集落が小さいので自分の村のなかで相手を見つけるのはむずかしかったんじゃないかと。近親婚にもなってしまいますしね。そのあたりはおそらく、本能的か経験からかはわからないですが、避けていたはず」
根岸「どうしてそう思うんですか?」
望月さん「これもアイヌの話なんですが、彼らには家族の文様っていうのがあったんですね。女の人はその文様の入った貞操帯みたいな下着を身につけていたんですが、これって多分、そういうことになったときに相手の男に気付かせるためにもあったんじゃないかと」
根岸「なるほど。男の方がその下着を見て『あっ! 親戚じゃんヤバい!』ってなるわけですね。土器や土偶を見ても、文様にこだわりを持っていたことは伺えますから、それが血の近さを伝えるものになっていたとしてもおかしくはなさそうな」
望月さん「その上で、私が思うに男はある時期になると村を出て、いろんな村を巡りながら、結婚相手を探していたんじゃないかと。いい相手が見つかったら、自分の村に連れて帰ったかもしれないし、その村で結婚をしてその村の人間になったかもしれない。女性が嫁入りするというよりは、自分たちの文化圏のなかで、男が動いていたと考える方が無理がない気がするんです」

根岸「村を出てパートナーを探しに行くのが、人生における通過儀礼のひとつだった可能性もありますよね。『そろそろお前も旅立つときが来た』とか長老に言われて」
望月さん「たとえばアイヌだったら、女の人は14~15歳で口元にバットマンのジョーカーみたいな刺青を入れます。男だったらやはり狩りですね。ある時期になるとクマを一人で倒さないといけないというミッションを課せられていたかもしれません。結婚相手を見つける旅もひとつの試練を伴う通過儀礼だったと考えることもできます」
根岸「麻酔なしで歯を抜く人もいたと聞いたことがありますが」
望月さん「婚姻との関係性はわかりませんが、実際、前歯を何本か抜いたり、歯を削って二股にするとか人体改造の方向に向かっている人骨は出ています。エクストリームな人もいたんですねえ」
「結納品」は縄文時代の結婚を紐解くカギになるか

根岸「僕は東京ですね」
望月さん「そうですか。関東の東の方は山形土偶とミミヅク土偶っていうのがすごくたくさん出土しているんですよ。これは僕が思うに、完全に流行りですね。ほかにも縄文晩期の青森の亀ヶ岡遺跡からは遮光器土偶というのが出土しているんですが、これも関東までフォロワーがいる。多分かっこよくて、みんながうらやましがったんじゃないかと」
根岸「土器はトレンドがあるって話でしたけど、土偶もそうなんですね」
望月さん「はい。土器や土偶っていうのは地域性がはっきりしているんです。そこに記された文様が地域のまとまりを示している。となると、これが婚姻で広まった可能性も十分あるんじゃないかと」
根岸「ああ、結納品の風習とかもあったかもしれないですね」
望月さん「縄文人って意外と行動範囲が広くて、たとえば新潟の糸魚川あたりでしかほとんど採取できないヒスイという鉱石が、なぜか全国に散らばっているんですよ。これが交易だったのか、物々交換だったのか、単にお土産だったのか、それとも結婚における結納品になっていたのか」
根岸「いくらでも想像を広げることができそうですね」
望月さん「結局、縄文時代は誰も見たことがないので、出土物からその世界を想像するしかない。逆に言えば、出土物からしか可能性を探れない。ヒントはたくさんあるけど、ヒントしかない。それが縄文時代なんですよね」
根岸「縄文時代のことがわかったらわかったで、さみしくなってしまうような気もしますね。今日は無茶なテーマにお付き合いいただきまして、ありがとうございました。望月さんの縄文愛を浴びることができて、最高の時間でした」
まとめ

今回、望月さんが縄文人を紐解く大きなヒントになると考えていた「アイヌ」をテーマにした『縄文ZINE』の最新刊(第4号/特集:アイヌに会いに)は、9/20頃に発行予定。配布先はサイトでチェックできるので、見つけたらぜひ手に取ってみてください。

縄文の夢は、終わらない。
【書いた人】

根岸達朗(ねぎし・たつろう)
ライター・編集者。発酵おじさん。
ニュータウンで子育てしながら、毎日ぬか床ひっくり返してます。
Twitter:onceagain74
■イマドキ結婚式事情
≫結納する? しない? 決め方・体験談

根岸達朗(ねぎし・たつろう)
ライター・編集者。発酵おじさん。
ニュータウンで子育てしながら、毎日ぬか床ひっくり返してます。
Twitter:onceagain74
■イマドキ結婚式事情
≫結納する? しない? 決め方・体験談
関連記事
 なんとなく不安の正体とは? 結婚を考え始めたカップルの心の変化
なんとなく不安の正体とは? 結婚を考え始めたカップルの心の変化
マイナビウエディング 編集部
2026/01/13 更新
 毎年好評の「軽井沢ウエディング合同バスツアー」2026年1月・2月に開催決定!参加者募集中
毎年好評の「軽井沢ウエディング合同バスツアー」2026年1月・2月に開催決定!参加者募集中
マイナビウエディング 編集部
2026/01/13 更新
 結婚指輪・婚約指輪探しにピッタリ! マイナビウエディングフェスタ2月1日開催【事前予約で特典あり】
結婚指輪・婚約指輪探しにピッタリ! マイナビウエディングフェスタ2月1日開催【事前予約で特典あり】
マイナビウエディング 編集部
2026/01/09 更新
 2026年は午年(丙午)! 午の持つ意味やカップルにオススメの2026年の過ごし方とは?
2026年は午年(丙午)! 午の持つ意味やカップルにオススメの2026年の過ごし方とは?
マイナビウエディング 編集部
2026/01/02 更新
 波瑠・高杉真宙の結婚から考える「職場結婚」のメリット・デメリット――アプリ恋愛が主流の今でも"やっぱりアリ"な理由
波瑠・高杉真宙の結婚から考える「職場結婚」のメリット・デメリット――アプリ恋愛が主流の今でも"やっぱりアリ"な理由
堺屋大地
2025/12/27 更新